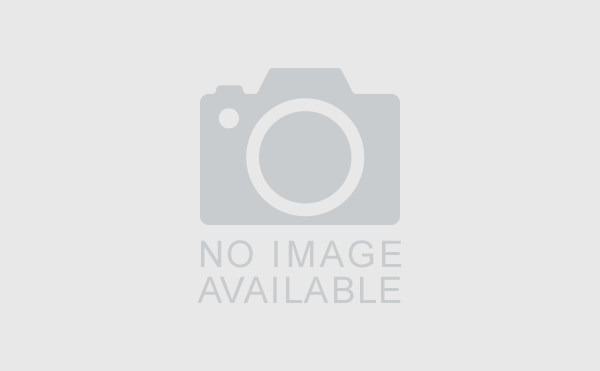舞台は総合芸術。音楽家の視点で気づいたライブと演出の可能性
かわさきタップフェスティバルでの気づき
今日は、かわさきタップフェスティバルの照明合わせでした。

稽古場やスタジオできっちり仕上げたつもりでも、本番に近い環境でやらないと気づかないことがたくさん!
本番前にリハがあるのも含めて、なんて出演者に手厚いイベントなんだろうと感服いたしました。
ところで先日、ある方がこう言っていました。
「舞台は総合芸術だよね」
最近の自分の経験を振り返ると、この言葉の重みをひしひしと感じています。
舞台はなぜ“総合芸術”なのか
最近、バンドのライブ以外への関わりが増えてきました。
特にダンスや演劇の舞台に接する機会が多く、「舞台は総合芸術」という言葉の意味を日々、肌で感じています。
演奏・演技・演舞だけじゃない。
照明、音響、衣装、台本、演出、客席との関係……“総合”の要素は挙げればキリがありません。
ライブにも、もっと「舞台」的こだわりを
アマチュアバンドのライブと比べると、スタンスに大きな違いを感じます(※感じ方には個人差があります)。
でも、バンドマンだって――いや、だからこそ。
一回のライブを“総合芸術”として捉えられたら、もっと素晴らしい表現ができるのではないか。
今日はそんな手応えを持ち帰ってきました。
もちろん、プロの現場では当たり前のようにこだわり抜かれているけど、
アマチュアだって、すでに本気でこだわってる人はたくさんいるんでしょうね。
今こそ、照明や空間との「共演」を
たとえば、街のライブハウスの照明オペレーターさんも、本当はもっとこだわりたいのかもしれない。
でも、わたし自身にそういう意識がなかったから、なんとなくの感じで合わせてくれてただけなのかも。分からないですけど。
特に「歌もの」なんかは歌詞があるし、曲ごとの展開もある。
演奏者の精神世界を、照明や演出で“具現化”することはきっとできるはず。
今までそういう視点を持ってなかった自分を、ちょっと悔やんでいます。
音楽家は音だけを奏でる存在なのか?
もちろん、
「音楽家ならそれを音で表現しろよ!」
という考えもあると思います。
でも、わたしは今――
それだけじゃもったいないと思っているんです。
これからは、演出という“楽器”も使っていきたい
よーし、今度はライブ空間の“演出”にも挑戦してみよう!
演出だって、音楽の一部になれるはずだから。