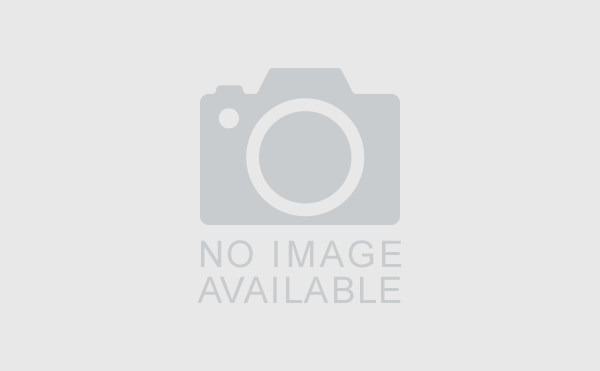古典文学のズレっぷり、そして半沢直樹の脳内上映会へ
古典の「ズレ」が生む魅力とは?
古典を読んでると、たまに「なにその行動?」という人物が出てくる。笛を吹きながら死地に向かう平敦盛とか、神社に参拝しに行ったのに、メインの本殿をスルーして裏の景色だけ見て満足して帰る坊さんとか、声が汚いって理由だけで人格ごと切り捨てる清少納言とか。さすがに仕打ちが雑すぎる。
これらは、たぶん当時の常識とはちょっとズレていたか、あるいは我々の常識の方がズレているのかもしれない。いずれにせよ、わけのわからない面白さがある。笑うしかないというか、「いや、そこはちゃんとしてくれよ」と言いたくなるような、あの感じ。
「倍返しだ!」がもたらす現代のお祓い儀式
テレビドラマの「半沢直樹」を見た。今さら。すごい面白かった。放送時は、なんでみんなそんなに騒いでんの?と思ってた。会う人会う人、みんなが満面の笑みで「倍返しだ!」とか言ってた記憶がある。
へー、そんなに流行ってるんだ。じゃあ絶っっっ対見ない! と、あらゆる半沢情報をシャットアウトして孤独をこじらせていた。
でも今ならわかる。あのドラマは、社会の様々な理不尽に対するエンタメ系お祓い儀式だったのだ。
原作とドラマ、二重写しの半沢体験
池井戸潤の原作本も買っちゃった。今さら。読んでみたら、ドラマと原作でけっこう違いがある。でも、読んでるそばから脳内で堺雅人が勝手に再生される。勝手に目力強めで喋る。勝手に怒る。勝手に土下座させる。
不思議なのは、もしドラマを見ずにいきなり原作から読んでたら、これ面白かったのか?ということ。銀行の腐った体質とか、正直興味ない。クソ上司の言動も、文字で読むとただただストレスでしかない。
でも読める。不思議なほど読める。読めるどころか面白い。全巻買っちゃうほどハマってる。なぜ?
視覚インストールで文章がログ化する現象
これはたぶん慣れなのだと思う。
最初にドラマで見て、あの世界観にどっぷり浸かってしまった。銀行という名の魔窟、上司という名の妖怪、会議室という名の戦場。その感覚が脳にインストールされてる。だから原作を読むと、自動的に映像が立ち上がる。堺雅人が喋り出す。香川照之が目をひんむく。
つまり、読書してるんじゃなくて、追体験してるのだ。脳内上映会。
そりゃ読める。面白いはずだ。文字が文字じゃない。全部あの世界の”思い出”になってる。原作の地味なやりとりが「おぉ、これあのシーンの元ネタか!」みたいに読み解けて、ちょっと得した気分になる。
平安時代に脳内上映会があったなら
で、ここで唐突に思い出すのが、さっきの古典の話。
当時の人は、あのコントみたいな展開をたぶん真剣に読んでいた(か、笑っていた)。我々が「なんでそこで笛!?」とツッコミたくなるのも、要はその世界を知らないからだ。
でも、もし古典の当時「平敦盛ダイジェスト映像」とか「清少納言ビジュアルノベル」みたいなものがあったら、たぶんそのあとに原文を読んでも理解度が爆上がりしたはず。脳内上映会、平安版。
つまり、先に視覚で世界観を叩き込むと、文章はぜんぶその世界のログになる。
違和感を感じてたことが、「ああ、こういう空気だったのね」と受け入れられる。
古典と現代ドラマに共通する「ズレの面白さ」
原作の半沢は、実はけっこう静かだ。理知的で、あまり怒鳴らない。冷静に詰めていく。でも不思議と脳内ではあのテンションで再生されるから、なんかこう、読むたびに理性と激情が二重写しになる。堺雅人と池井戸潤の合同作業。
そして不意に出てくる「倍返しだ!」。それがまた効く。普通の文体に、急に飛び込んでくる熱量。これはもう文学的パンチラインだと思う。清少納言が「にくし」と言うのと同じノリで「倍返しだ!」と言ってる。たぶんあれは文章表現における踵落しなのだ。
古典と現代の物語、こんなにも時代が離れているのに、どちらも「ズレ」の面白さで読むことができる。そしてそのズレが、世界観を逆に濃くする。
…などと偉そうなことを言ってみたけれども、要は、わたしは半沢直樹にハマっている。今さら。
関連記事
「空気感」を身体で感じるという点では、こんな街の情緒もまた興味深いです。
→ 鶯谷感。透明感の対極にある情緒の結晶