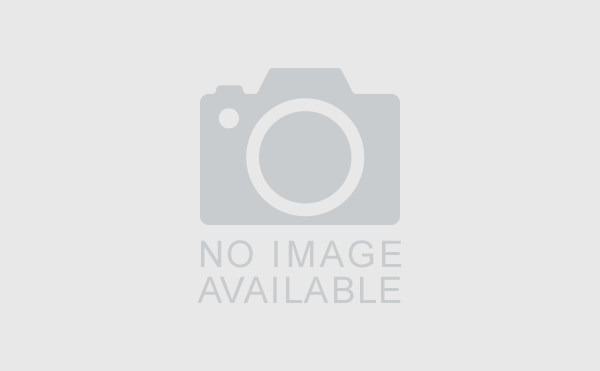鶯谷感。透明感の対極にある情緒の結晶

「透明感」とは違う、鶯谷で感じる情緒の衝撃
「透明感」というものを定義するのは難しい。でも、その情緒を共有することは案外できる。ならば、わたしが感じたこの「鶯谷感」も、きっと共有できるはずだ。そう信じて書き始める。
JR鶯谷駅の南口に降り立った瞬間、思わず声が出た。「おぉ、なんという鶯谷感!」
赤提灯が放つ、ある種の“美しさ”
その一言に尽きる。何かが胸を打ったのだ。でもそれは、感動の涙を誘うような壮麗な景色ではない。むしろ線路沿いに並ぶ赤提灯の飲み屋街。その小汚さ(誉め言葉)が、わたしの心をグッと掴んだのだ。
赤提灯は、小綺麗である必要がないどころか、小汚いほどいい。それが赤提灯という存在の透明感、いや、「鶯谷感」を際立たせる。そして、その光景にひとしきり感嘆した後、駅の連絡通路へと足を踏み入れた。
駅の連絡通路から見た、ネオンの宝石箱
連絡通路から望むラブホテル街のネオンは、まるで都市の下品さ(誉め言葉)を凝縮した宝石箱だ。煌びやかな光がどこか雑然と、むしろ無秩序を楽しむように放たれている。「ゆうべはおたのしみでしたね」の言葉を、光だけで表現しているような、そんなネオン。ここまで開き直られると、もう美しいとしか言いようがない。
鶯谷感とは「これでいいんだよ」と包み込む空気
鶯谷感とは何か。それは、この街の全てが「これでいいんだよ」と語りかけてくる包容力ではないだろうか。酔っ払い、性風俗、街灯下のゲロ。そう、それでいいのだ。整った風景や洗練された空気感とは真逆にある、雑然さと胡散臭さが絶妙な調和を奏でる。鶯谷感は、この混沌の中に宿るのだ。
混沌の中にある、鶯谷の美学
透明感のように清らかな情緒も美しいが、鶯谷感のように混沌とした情緒もまた素晴らしい。どちらも言葉で完全に定義することは難しいが、降り立った瞬間に感じる情緒が、何よりその土地を物語るのだ。
鶯谷感を味わう方法
鶯谷感をもっと深く味わいたければ、まず一杯ひっかけるのがいいだろう。赤提灯の中に入り、ホッピーでも飲みながら鶯谷という街の情緒を舌で感じる。それがこの街を知る最短ルートだ。もし問題があるとすれば、わたしはお酒を飲むことができないということだけだ。
関連記事
「ズレ」に惹かれる感覚は、古典文学やテレビドラマにも通じます。
→ 古典文学のズレっぷり、そして半沢直樹の脳内上映会へ