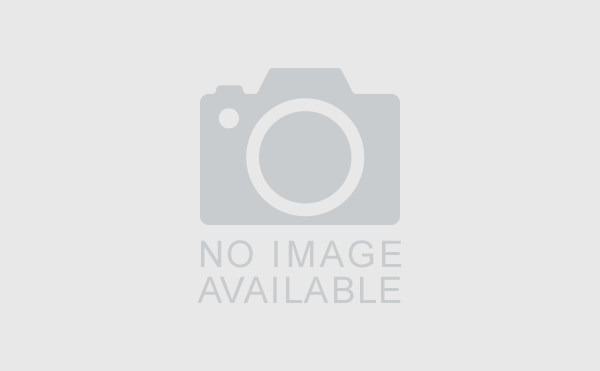俳優塾「かざん塾」で学んだ世阿弥の言葉と音楽のつながり
世阿弥の哲学と演劇のワークショップ
立本夏山さん主催の俳優塾「かざん塾」のワークショップに参加させて頂きました。
「秘すれば花」「離見の見」など、世阿弥の言葉を手掛かりに、様々な演劇のワークを体験。
演劇の文脈としては理解が及ばず全く動けず…。脳内では毎秒3回ずつ「???」が量産され、もはや内なるわたしが体育座りして震えていました。
ミュージシャン視点で見る世阿弥の教え
でも!
これを楽器演奏の文脈に変換すると腑に落ちることばかり。
ミュージシャンならきっと全員、頷きすぎて首の筋肉で発電できるんじゃないかと思うくらいの納得感。ほんとに驚くほど理解しやすい。
序破急なんて、Aメロ・Bメロ・サビ・ブリッジ・Cメロ・エンディング、みたいな考え方をすると何の抵抗もなく腑に落ちるのです。どういうことか詳しく知りたい方はぜひワークショップに参加してください。
たぶん世阿弥先生とサシで居酒屋に行っても、一品目が出てくる前に意気投合して、カルピスソーダ3合くらい空ける自信あります。
和太鼓奏者と俳優の演奏の違い——「花」と「離見の見」
例えば、俳優さんやダンサーさんが叩く和太鼓。
和太鼓奏者の人たちのような超絶な技術や手数がなくても、お客さんの心を揺さぶる素晴らしいパフォーマンスとして成立してしまうのです。少なくともわたしは、和太鼓奏者の方の和太鼓演奏よりも、俳優さんの和太鼓演奏の方が心に響いてしまうのです。(優劣ではなく、わたしの好みの話です)
なぜ? どうして? 神か? ズルいのか?
その秘訣が「花」であり「離見の見」なのではないか、という解釈を持ち帰ってきました。カバンの中に詰め込んで帰ってきました。パンパンです。
わたしの理解の仕方はこんな感じ
立本夏山さんが能のお稽古中、師匠の方に「稽古の回数が足りない」と指摘されたとのこと。
以下、ツイートを引用させていただきます。
演劇の稽古場では稽古の回数は重視されない。このお言葉を聞いてわたしが思ったこと。
演劇は音楽のセッションに近いのかもしれない。曲のキーだけ決めて、メロディーもリズムもテンポも、各プレイヤーが音で会話して音楽を作り上げていく。誰かの頭をスリッパで思い切り叩く音さえ楽器として歓迎される。
能は様式美を重視するメタルに近いのかもしれない。演奏のブレなど微塵も許さない。針の穴に糸を通すような精密な速弾きギターと、ドラムはツーバスに決まってんだろ。あとオマエはメイクの練習してこい!みたいな。
俳優塾「かざん塾」はミュージシャンにもおすすめ!
いわゆる[演劇論]みたいな話になると、わたしはすぐに「自分が石化してしまったのでは」と疑い始めるタイプなのですが、次の文章をご覧ください。
「ただ立っているだけなのに、何故か目が離せない、ついついその俳優さんを目で追ってしまう、ということありますよね。
いわゆる『存在感』とも言われるようなものですが、それって一体何なのでしょうか」
(立本夏山オフィシャルサイトより引用)
こんな言葉にしてもらうと、心がウズウズと震えてきませんか?
これはミュージシャンこそ静かに浴びるべき演劇の栄養…! と、ペットボトルのアールグレイがいつもよりやさしく喉を通りました。
立本夏山さんが、優しく根気強く丁寧に教えて下さいますよ。ご興味持たれた方はぜひぜひ。オススメです!
🔗 かざん塾 公式サイト