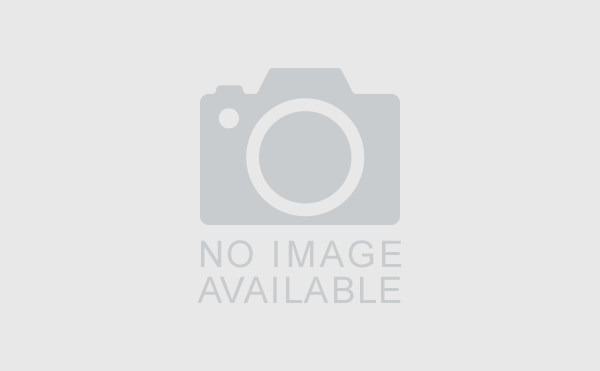略語の寂しさ。ブルマンとサントラ、そしてウの疎外感
キリマンとブルマン、略語の運命
キリマンジャロを「キリマン」と略すのは理解できる。
ジャロの部分をスパッと切り捨てるその潔さ、言いやすさのバランス。略語として成立する要件を見事に満たしている。だが、ブルーマウンテンを「ブルマン」と略すことに関しては、どうしても納得がいかない。
「ブルマウ」ではダメなのか?消される音の悲哀
ブルマン――ブルーがあるのにウがいない。
マウンテンの「マ」と「ン」が堂々と略語の中に居座る中、ウはどこへ行ったのか? なぜ彼だけが仲間外れにされたのか。その理不尽さを想像すると、ブルーマウンテンの山頂で吹き荒れる寂しい風が聞こえてくるようだ。
「ブルマウではないのか?」と問いかけたい。略語にしてもウを残してあげれば、マウンテン全体の響きがもっと尊重されるのではないか。だが現実は「ブルマン」である。ウは切り捨てられ、寂しさを胸に抱えて山を下るしかないのだ。
「サントラ」「イントラ」も同じ運命
この憤りを感じるのは、ブルマンだけではない。
たとえば「サウンドトラック」が「サントラ」になる瞬間、トラックという後半部分が略語の主役に据えられ、サウンドがまるで添え物のように扱われるのはどうなのか。サウンドがなければ、ただのトラック。なのに「サントラ」という略語は、サウンドの意義を半ば無視している。
そして「インストラクター」の略語である「イントラ」。これはもう、イントロか何かと勘違いしてしまうほどの潔さだ。インストラクターの膨大な努力や知識が、真ん中のスを抜いた中途半端に形に圧縮されるという事実に、わたしは哀愁を禁じ得ない。
略語の影に消えた音たちを思う
略語とは効率化の産物だが、その裏にある犠牲――消される音や文字への想像力を忘れてはならないのだ。
他人にとってはどうでもいい、この略語への憤り。
わたしがこうして「ブルマウ」と「サウンドの意義」を唱えても、たぶん誰も気にしないだろう。でも、このくだらない問いかけをすることが、わたしにとって略語を使いながらも消されていった音たちに対する供養のような気がしてならないのだ。
略語への供養——「ウ」に想いを馳せる
コーヒーを注文するとき、「ブルマン」と口にしたら、心の中でそっと「ウ」に想いを馳せる。きっとそんな誰も聞いていない供養が、略語の寂しさをほんの少しだけ癒してくれるのではないか。
略語よ、寂しさを抱えながらも、これからも日々の言葉を短縮し続けてくれ。だが、忘れるな。略された部分に眠る、消えたはずの音の声を。
関連記事
言葉の響きをもっと楽しむなら
ブルーマウンテンの「ウ」、サントラの「サウンド」、イントラの「ス」…。
消えた音に想いを馳せるのも良いけれど、響きだけを愛でる贅沢 もある。
そんな 「言葉の音の魔力」に惹かれるあなたへ。
🔗 【ピニャコラーダの響きとわたしの小さな革命】
ピニャコラーダの響きが頭から離れない。意味を知らずに楽しむ贅沢とは?